






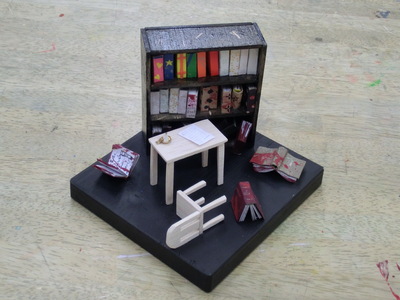



投稿日:2014.03.01
「楽しい人生を送ってください。二つの道ができたとき、難しいほうにチャレンジしてみてください。私はそうやって生きてきて良かったと思っています。」これは二学期の最後にある先生がおっしゃった言葉である。この言葉は私に訴えかけているような、心に響くような、本当にぐっとくる言葉だった。一つの物事で良い方向にいくか、悪い方向にいくか、その一つの決断が自分の人生を変えるようなことだってあるだろう。先生方がおっしゃった通り、難しい方にチャレンジする方がいいと思う。難しいことにチャレンジするというのはとても勇気がいることであり、簡単な方へ、楽な方へ、と行きたがる自分もいると思う。もしそこで楽な方を選んでしまったとしたら、自分に後悔してしまうのではないだろうか。しかし、物事がおわってからでは、もう遅いのだ。難しい方にチャレンジして、努力して、努力して、本当に自分の限界まで努力して、成功した。このことに悔しさというものは一つも残らないことは今の自分でも分かる。苦しくてもその中で努力したという達成感と自分への誇り、そして一番大きいのはうれしさだと思う。
(中3)
投稿日:2014.03.01
小学校の卒業文集にこんなことを書いた。「私は将来、獣医か動物看護師になりたいです。動物が好きで、どんなところが好きかというと、今問題になっている公害などでどんなに苦しくても頑張って一生懸命生きようとしているところです。私はそんな動物たちの姿を見て、『守ってあげなきゃ、助けてあげなきゃ。』と思いました。まだ獣医になれる自信はないけれど、動物たちの声に耳をかたむけ、国境なき獣医師団にも入れたらいいなと思っています。」見返してみれば自信のなさが滲み出ている発言が多々ある。メスを握って血や内臓を見ても平気でいられる気がしない。学力的にも程遠い。国外に行く勇気も行動力もないと思う。しかし、才教学園に入学して少しは自信を持てるようになった。オーストラリアへ修学旅行へ行って外国の人とのコミュニケーションのとり方を知ったし、運動嫌いだったのを克服して体力もつけた。小学生のときは英語を別次元のように思っていたが、勉強しているうちにやや得意な科目であることも分かった。人間的にも「挨拶」「礼儀」「上下関係」について身についた。なにより自分との付き合い方がわかった。友人関係で悩んだり、テストの点数が悪すぎて自己嫌悪に陥ったりしたこともあった。一時、私は人間として存在することが嫌で恥ずかしく思っていた。しかし今は人間だからできること、人間だからやらなければならないことに気付いたから迷わない。助けを必要とする動物たちのため、夢を諦める訳にはいかない。
(中3)
投稿日:2014.03.01
才教学園での三年間は、僕にとってとても充実したものだった。他の学校ではまずできない、さいきょう祭、体育祭、プレゼンテーションコンテスト、オーストラリアでの修学旅行など、一つ一つの貴重な体験が、その都度僕を大きく成長させてくれたと思う。積極的になり、他人を導ける人になる。自分を甘やかさず、他人から信頼される人間になる。そして自分の好きな分野で他人に精一杯尽くす。これが、ぼくが才教学園での三年間で見つけた自分の生き方だ。
(中3)